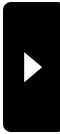2017年07月27日
将来について考える
昨日、「生涯生活設計セミナー」という研修を受けてきました。
勉強になったし、いろいろ考えさせられました。
これまで自分のキャリアプランというのは、具体的に立てられていたつもりなんだけど、ファイナンシャルプランというか、お金の話はアバウトだったので、今回のセミナーは参考になりました。
「やっぱり、もう一度留学に行きたい。しっかり、研究者としての知識やスキルを学びたい」という思いがあって、妻とも相談しながら留学したいと思っていました。 いや、今もできればしたいんだけど。。。 もう一つの道の方が自分にも家族にもメリットが大きいんじゃないかなーと考えるようになりました。
なんだろ。研究!研究!っていう研究(笑)はあまり向いていないんだけど、教師には授業を教えるだけじゃなくて、どのように教えた方が効果的か常に追究し続ける必要があると思っていて、Teacher-Researcherとして成長したいという思いがあります。 そのためには、ずっと学校現場にいるんじゃなくて、どっぷりとアカデミックな世界につかるのもどっかのタイミングでは必要だと思っています。 特に、研究者としての未熟さを強く感じるので(もちろん、実践の面もまだまだ未熟ですが。。。)、ハワイ大学のSecond Language Studies(SLS)の修士課程で学びたいという思いがあります。
想いがあるのは良いこと! 想いがなければ、どんな道も開けないはずだから。
でもでも、やっぱり、想いだけじゃなくて、他の要素も検討しながら自分の人生設計をしなきゃいけないですよね。
あー、自分の人生設計という言葉を使っている。。。
家族の人生設計というのかな。 妻と一緒に描いていかなきゃいけないと感じています。
昨日のセミナーでは、人生を100年というスパンで考えたときに、どのくらいの費用が必要なのかシミュレーションしました。
子ども3人(ほしい!)の教育費。 住宅ローン。 保険。 家族との旅行とか
そんなのを考えていたら、2年という長期間、俺も妻も無休で物価の高いハワイで生活するってかなり厳しいー!!
家族で留学したかった理由は・・・
○研究者としてスキルアップ
○英語力のアップ
○家族にも異文化で生活してほしい
という感じ。
これって、他の道でも実現できるんじゃないか? って考えるようになりました。
まずは、実践に根差した研究をしっかりしていく。 留学したらスキルアップするだろう。みたいな甘い考えじゃなくて、せっかく現場にいるのだから、現場でしかできない研究にチャレンジする。志を高く持っていたら、指導してくださる先生に出会えるし、その中でスキルアップできるはず。
留学したら英語力がアップするだろうーっていうのも甘えだ!笑 まずは、英語を学習する習慣をつけないと。
海外の日本人学校に赴任しよう!そしたら、家族で海外の生活を経験できる。 子どもにとっても大きな経験だと思う。
という感じに考えるようになりました。 まずは、夏季休業中にしっかりと英語の勉強をします。 授業準備とか他の分掌を言い訳にしないぞー!
しそうだなー。。。 しないぞー!!
ファイナンシャルプラン。もっともっと妻と相談しなきゃ。
勉強になったし、いろいろ考えさせられました。
これまで自分のキャリアプランというのは、具体的に立てられていたつもりなんだけど、ファイナンシャルプランというか、お金の話はアバウトだったので、今回のセミナーは参考になりました。
「やっぱり、もう一度留学に行きたい。しっかり、研究者としての知識やスキルを学びたい」という思いがあって、妻とも相談しながら留学したいと思っていました。 いや、今もできればしたいんだけど。。。 もう一つの道の方が自分にも家族にもメリットが大きいんじゃないかなーと考えるようになりました。
なんだろ。研究!研究!っていう研究(笑)はあまり向いていないんだけど、教師には授業を教えるだけじゃなくて、どのように教えた方が効果的か常に追究し続ける必要があると思っていて、Teacher-Researcherとして成長したいという思いがあります。 そのためには、ずっと学校現場にいるんじゃなくて、どっぷりとアカデミックな世界につかるのもどっかのタイミングでは必要だと思っています。 特に、研究者としての未熟さを強く感じるので(もちろん、実践の面もまだまだ未熟ですが。。。)、ハワイ大学のSecond Language Studies(SLS)の修士課程で学びたいという思いがあります。
想いがあるのは良いこと! 想いがなければ、どんな道も開けないはずだから。
でもでも、やっぱり、想いだけじゃなくて、他の要素も検討しながら自分の人生設計をしなきゃいけないですよね。
あー、自分の人生設計という言葉を使っている。。。
家族の人生設計というのかな。 妻と一緒に描いていかなきゃいけないと感じています。
昨日のセミナーでは、人生を100年というスパンで考えたときに、どのくらいの費用が必要なのかシミュレーションしました。
子ども3人(ほしい!)の教育費。 住宅ローン。 保険。 家族との旅行とか
そんなのを考えていたら、2年という長期間、俺も妻も無休で物価の高いハワイで生活するってかなり厳しいー!!
家族で留学したかった理由は・・・
○研究者としてスキルアップ
○英語力のアップ
○家族にも異文化で生活してほしい
という感じ。
これって、他の道でも実現できるんじゃないか? って考えるようになりました。
まずは、実践に根差した研究をしっかりしていく。 留学したらスキルアップするだろう。みたいな甘い考えじゃなくて、せっかく現場にいるのだから、現場でしかできない研究にチャレンジする。志を高く持っていたら、指導してくださる先生に出会えるし、その中でスキルアップできるはず。
留学したら英語力がアップするだろうーっていうのも甘えだ!笑 まずは、英語を学習する習慣をつけないと。
海外の日本人学校に赴任しよう!そしたら、家族で海外の生活を経験できる。 子どもにとっても大きな経験だと思う。
という感じに考えるようになりました。 まずは、夏季休業中にしっかりと英語の勉強をします。 授業準備とか他の分掌を言い訳にしないぞー!
しそうだなー。。。 しないぞー!!
ファイナンシャルプラン。もっともっと妻と相談しなきゃ。
Posted by saygo at
17:57
│Comments(0)
2017年07月21日
交流学習 with T中学校 1年生 パート①
昨日で1学期が終わりました。 あっという間でした。早い!! こうやって夏休みも終わっていくのかなー。
有意義に過ごしたいです!!
先週は3つの交流学習があって、なんだか、子ども達もそうだけど、私自身も達成感があります。
赴任してから、他の離島の中学校とインターネットを通しての交流学習を継続しています。今年で、3年目!
相手の学校の先生は、学生のときからずっと英語教育について語り合ってきた友だちなので、お互いに何を考えているかわかっていて、打ち合わせもLINEで少しメッセージを交換するだけで、できちゃいますw
互いに刺激し合える(と俺は思っている)仲間がいることは本当に幸せで、こんな仲間の輪を少しずつ広げられたらと思っています。
先週の交流学習3つというのは・・・
① 自己紹介(1年生)
小さな島では生徒はお互いに知り合っているので、あんまり自己紹介をする意味がないw なので、他の中学校に自分のことを紹介するという目的。
② 自分の島の紹介(3年生)
教科書にある日本の文化紹介というのをちょっとアレンジして、自分の島の紹介。15の春に島を離れる子たちだからこそ、自分の生まれ育った島の良さを改めて認識してほしい。そして、それを英語で世界に発信できる子になってほしいという願いから。
③ インドの文化について(3年生)
教科書のLesson 3-CDはインドの文化についての内容なので、うちのALTの友だちでトリニダード出身でインドのバックグランドを持つALTにいろいろ教えてもらいました。私自身、下調べをして臨んだんだけど、それでも新たに学ぶことがあって、おもしろかった。うちのALTも自分自身も学ぶことがあったといってました。 やっぱり、教科書の指導書とかインターネットの情報だけじゃなくて、その文化背景を持つ人から直接学ぶって大切だと思いました。
という感じの交流学習でした。
今回は、1年生の取り組みをふり返りながらまとめていきたいと思います。
1年生の1学期のパフォーマンス・テストとして、T中学校の生徒に自己紹介をするという課題を設定しました。
目標は1分間の自己紹介! それと、相手の自己紹介をメモを取りながら聞き取ること。
1分って、案外と長いです。英語教師でもネタが尽きてきて、途中で「えーっと・・・・」ってなったりします。笑
それでも、中学校の初期の段階で「流暢性」を意識した指導が大切だと思うので、英語の量を出させることを意識しています。
そのために意識して指導したことは・・・
①音読
いろんな種類の音読をしながら、英語を読むことに慣れさせたり、覚えることへの抵抗をなくすように指導してきました。
最初は英語を読む「速さ」に意識して取り組んでもらいます。
〇ペアで速さを勝負する「音読バトル」は子ども達も好きな活動で、必死に取り組んでくれます。
〇人数が少ないので、何回かバトルをしたら、飽きるのでハンドをつけます。
じゃんけんで勝った方が、負けた方の3~5秒後にスタートする。みたいな感じで。
生徒が読むのに慣れてきたら、「意味」を意識しながら読んだり、覚えることを意識した音読に移ります。
〇リード・アンド・ルックアップ
〇日本語→英語 教師が日本語で読み上げ、生徒は英語で読む。
〇レペティッション 閉本した状態で、教師の後に繰り返す。生徒は教師が読んでから5~10秒後に繰り返す。
などなど、いろんな音読をしながら、できるだけ飽きずに、楽しみながら力がついていくのを目指しています。
単元(レッスン)が終わると、音読テストがあるんですが、すべての生徒が全部のパートを暗記しています。
ホントに意欲的で感心します。
②スピーキングの帯活動「ベしゃりマスター」
以前の投稿にも書いたのですけど、スピーキングの帯活動として「べしゃりマスター」を入れました。
じゃんけんで勝った方が自己紹介を設定された時間で行う活動。逆に言うと時間内はなんとかしゃべり続けないと行けない活動です。
負けた方は、あいづちなどのリアクションをしながら聞きます。まだまだ、聞く姿勢は指導不足ですが。。。
時間の設定は最初は30秒から始めました。やはり、30秒でもキツくて、しゃべりつづけるのはできなかったのですが、ペアを変えてやっていくうちに、話す内容の幅が広がっていって、30秒、45秒、最後には1分と継続できるようになってきました。
1分間話すことができるようになったのは、期末テストの英作文の課題が大きかったのじゃないかなーって思っています。
③期末テストでの英作文の課題
定期テストの英作文は、事前に課題を知らせて、教師またはALTのアドバイスを受けてから、それを覚えて書く方式にしています。
これは「佐賀メソッド」のワークショップが沖縄で開催されたときに学んだ方法です。
即興での英作文の力も大切だと思うんですが、中学の段階では覚えたのを書くというので、スローラーナーにも「やってみよう!」と思えるような課題にする方が良いんじゃないかと思っています。
今回は流暢性、つまり文の量を重視したかったので、加点方式にしました。1文2点もらえて、書けば書くほど点数が上がる。だけど、文法に大きなミスがあった場合は減点するという感じです。
生徒にも事前に伝えていたので、最後までねばり強く書き続けていました。
④4技能を統合した指導
交流学習の前日は以下のような流れで指導しました。
〇べしゃりマスター(スピーキング・リスニング)
〇ノートに自己紹介を書く(ライティング)
〇ノートを回して、お互いに自己紹介を読む合う。(リーディング)
読んでいて、「いいな!」って思うところには◎をつけて、間違いだと思うところは直してあげるか、下線を引いてあげる。
ただ読ませるのではなくて、読むポイントを与えたので、みんな真剣に読んでくれたと思います。
〇自分の自己紹介を最終チェック
〇プレ発表(スピーキング・リスニング)
〇ふり返り・目標の設定
iPadを使って、自分たちの発表を見ながらふり返って、交流学習の目標を立てました。
ただ、時間がオーバーしてしまったので、昼休みに集まってもらって、時間に追われながらのふり返りになってしまいました。。。
タイムマネジメントが・・・。 昼休みに集まってくれる、この子達に感謝です。
いろいろ自分なりに工夫しながらやったつもりです。 子ども達がよくがんばってくれたので、流暢性については去年よりもよくなっている気がします。 ふり返りをもっと大切にして、メタなレベルから自分のパフォーマンスを分析できるように指導したいと思います。
次は、三単現を学習した後に、友だちの紹介や好きな有名人の紹介で交流学習をしたいと思っています。
有意義に過ごしたいです!!
先週は3つの交流学習があって、なんだか、子ども達もそうだけど、私自身も達成感があります。
赴任してから、他の離島の中学校とインターネットを通しての交流学習を継続しています。今年で、3年目!
相手の学校の先生は、学生のときからずっと英語教育について語り合ってきた友だちなので、お互いに何を考えているかわかっていて、打ち合わせもLINEで少しメッセージを交換するだけで、できちゃいますw
互いに刺激し合える(と俺は思っている)仲間がいることは本当に幸せで、こんな仲間の輪を少しずつ広げられたらと思っています。
先週の交流学習3つというのは・・・
① 自己紹介(1年生)
小さな島では生徒はお互いに知り合っているので、あんまり自己紹介をする意味がないw なので、他の中学校に自分のことを紹介するという目的。
② 自分の島の紹介(3年生)
教科書にある日本の文化紹介というのをちょっとアレンジして、自分の島の紹介。15の春に島を離れる子たちだからこそ、自分の生まれ育った島の良さを改めて認識してほしい。そして、それを英語で世界に発信できる子になってほしいという願いから。
③ インドの文化について(3年生)
教科書のLesson 3-CDはインドの文化についての内容なので、うちのALTの友だちでトリニダード出身でインドのバックグランドを持つALTにいろいろ教えてもらいました。私自身、下調べをして臨んだんだけど、それでも新たに学ぶことがあって、おもしろかった。うちのALTも自分自身も学ぶことがあったといってました。 やっぱり、教科書の指導書とかインターネットの情報だけじゃなくて、その文化背景を持つ人から直接学ぶって大切だと思いました。
という感じの交流学習でした。
今回は、1年生の取り組みをふり返りながらまとめていきたいと思います。
1年生の1学期のパフォーマンス・テストとして、T中学校の生徒に自己紹介をするという課題を設定しました。
目標は1分間の自己紹介! それと、相手の自己紹介をメモを取りながら聞き取ること。
1分って、案外と長いです。英語教師でもネタが尽きてきて、途中で「えーっと・・・・」ってなったりします。笑
それでも、中学校の初期の段階で「流暢性」を意識した指導が大切だと思うので、英語の量を出させることを意識しています。
そのために意識して指導したことは・・・
①音読
いろんな種類の音読をしながら、英語を読むことに慣れさせたり、覚えることへの抵抗をなくすように指導してきました。
最初は英語を読む「速さ」に意識して取り組んでもらいます。
〇ペアで速さを勝負する「音読バトル」は子ども達も好きな活動で、必死に取り組んでくれます。
〇人数が少ないので、何回かバトルをしたら、飽きるのでハンドをつけます。
じゃんけんで勝った方が、負けた方の3~5秒後にスタートする。みたいな感じで。
生徒が読むのに慣れてきたら、「意味」を意識しながら読んだり、覚えることを意識した音読に移ります。
〇リード・アンド・ルックアップ
〇日本語→英語 教師が日本語で読み上げ、生徒は英語で読む。
〇レペティッション 閉本した状態で、教師の後に繰り返す。生徒は教師が読んでから5~10秒後に繰り返す。
などなど、いろんな音読をしながら、できるだけ飽きずに、楽しみながら力がついていくのを目指しています。
単元(レッスン)が終わると、音読テストがあるんですが、すべての生徒が全部のパートを暗記しています。
ホントに意欲的で感心します。
②スピーキングの帯活動「ベしゃりマスター」
以前の投稿にも書いたのですけど、スピーキングの帯活動として「べしゃりマスター」を入れました。
じゃんけんで勝った方が自己紹介を設定された時間で行う活動。逆に言うと時間内はなんとかしゃべり続けないと行けない活動です。
負けた方は、あいづちなどのリアクションをしながら聞きます。まだまだ、聞く姿勢は指導不足ですが。。。
時間の設定は最初は30秒から始めました。やはり、30秒でもキツくて、しゃべりつづけるのはできなかったのですが、ペアを変えてやっていくうちに、話す内容の幅が広がっていって、30秒、45秒、最後には1分と継続できるようになってきました。
1分間話すことができるようになったのは、期末テストの英作文の課題が大きかったのじゃないかなーって思っています。
③期末テストでの英作文の課題
定期テストの英作文は、事前に課題を知らせて、教師またはALTのアドバイスを受けてから、それを覚えて書く方式にしています。
これは「佐賀メソッド」のワークショップが沖縄で開催されたときに学んだ方法です。
即興での英作文の力も大切だと思うんですが、中学の段階では覚えたのを書くというので、スローラーナーにも「やってみよう!」と思えるような課題にする方が良いんじゃないかと思っています。
今回は流暢性、つまり文の量を重視したかったので、加点方式にしました。1文2点もらえて、書けば書くほど点数が上がる。だけど、文法に大きなミスがあった場合は減点するという感じです。
生徒にも事前に伝えていたので、最後までねばり強く書き続けていました。
④4技能を統合した指導
交流学習の前日は以下のような流れで指導しました。
〇べしゃりマスター(スピーキング・リスニング)
〇ノートに自己紹介を書く(ライティング)
〇ノートを回して、お互いに自己紹介を読む合う。(リーディング)
読んでいて、「いいな!」って思うところには◎をつけて、間違いだと思うところは直してあげるか、下線を引いてあげる。
ただ読ませるのではなくて、読むポイントを与えたので、みんな真剣に読んでくれたと思います。
〇自分の自己紹介を最終チェック
〇プレ発表(スピーキング・リスニング)
〇ふり返り・目標の設定
iPadを使って、自分たちの発表を見ながらふり返って、交流学習の目標を立てました。
ただ、時間がオーバーしてしまったので、昼休みに集まってもらって、時間に追われながらのふり返りになってしまいました。。。
タイムマネジメントが・・・。 昼休みに集まってくれる、この子達に感謝です。
いろいろ自分なりに工夫しながらやったつもりです。 子ども達がよくがんばってくれたので、流暢性については去年よりもよくなっている気がします。 ふり返りをもっと大切にして、メタなレベルから自分のパフォーマンスを分析できるように指導したいと思います。
次は、三単現を学習した後に、友だちの紹介や好きな有名人の紹介で交流学習をしたいと思っています。
2017年06月04日
特別支援を要する子の指導みたいなお話 メモメモ
リフレクションをもとにした授業改善に取り組んでいて、最近興味を持っていること、ちょっと悩んでいることを書いていきます。
読み書きに困り感がある生徒の指導が課題。
最近思っているのは、授業のユニバーサルデザイン(UD)の視点をもっと大切にしていくこと、それから個別の支援が必要だろうなーって思っています。
UDは、特別な支援が必要な子に対する手立てが、他の子にも助かる手立てで、みんなが「わかる」とか「できる」っていう授業をめざそうって考え方です。(俺の理解ではw) 3つの視点を大切にしていたと思います。
①視角化:映像、写真、絵、実物教材とか、実際に演じてみるとか。けっこう人間って視覚的な情報に頼ってる部分大きいみたいなので、しっかりと見て、確認できることって大切みたい。
②焦点化:「1時間、1目標」みたいな感じで、1時間になんでも詰め込みすぎないで、シンプルにすることがわかりやすさにつながるみたいな。
③共有化:子ども達が理解したことを(ペアとかで)共有することで、みんな一緒に進んでいくってこと。プラス、互いの意見を交換しながら学び合うってことだったと思う。
今は、前よりもこれらの視点を意識して授業計画しているつもりです。
①視角化
英語の授業では特に視覚教材って大切。 題材に興味を持ってもらったり、意味を類推させるために必要になります。
前からパワポを使っていたんだけど、できるだけシンプルに!っていうのを意識していました。 やっぱり、忙しいとパワポのアニメーションにこだわるのはできないし、それだったら、シンプルに写真を並べるだけでも生徒の興味・関心を高めたり、理解を深められるようなClassroom Englishのスキルを上げた方が良いなーって思ってました。
でも、最近は、もっとわかりやすさを追求しよう!ってことで、けっこうアニメーションにこだわったり、見やすさを意識した色を使ったり、注目しやすいように色を変えるとか工夫しています。 今思っているのは、パワポのスキルをアップさせて授業準備の効率的にできるようにしようってことです。 あと、1回苦労して作ると、あとは同じアニメーションの設定で、コピペするだけでいいので、だいぶ授業準備の時間は短縮されました。 パワポのスキルがあがると、あんな活動もいいなーとかいろいろアイディアがでてきます。 今年はこだわってやっていきたいなーって思っています。
あとは、パワポだけでなく、関連する映像とかをもっともっと使えたらいいなー。生徒の興味を引きつけるだけじゃなくて、題材をもっと「自分事」として捉えられるようにできたらいいなー。今は、まだまだ教科書をどうわかりやすか教えるかってところの方に意識が向いていて、教科書を超えて、子ども達と学ぶってところをやりたいなー。でも、まだちょっと時間がかかりそう。。。
②焦点化
学生のころから、「めあて」とか「目標」を示すのがあんまり好きじゃないタイプでした。「英語を勉強!勉強!勉強!みたいにしたくない。楽しみながら自然と身につけてほしい!」みたいな考えがあったのでw
今も最初から目標を提示すると「マジックの種明かし」をしているような感じで、個人的にしっくりこないので、できるだけ導入を終えて興味・
関心が高まったときに提示したいなーと思っています。 だけど、そうしていたら、目標を提示するのを忘れたりもするし、復習に予想以上に時間がかかってしまったときに、授業の終わり20分前で目標の提示とかあるんだけど。。。 どうしたらいいんですかね。。。
とりあえず、特別支援教育の視点から目標を提示することは大切みたいです。勉強のできる「勘のいい子」は目標の提示なしでも、自然と「こんなことを勉強するんだー」っていうのがわかるみたいですが、特別な支援の必要な子やスローラーナー(Slow Leaner)には、方向性がわからないままさまよっているような感じだそうです。だから、できるだけ授業の早い段階で目標を提示したいのですが。。。 この辺はまだまだ工夫が必要です。
③共有化
なんか、書いていて気づいたけど、授業中にこの視点をあまり意識してこなかったなーと。 最近、3年生の授業でT / F Questionsをやったとに、答えの理由をペアで確認してもらいました。 そしたら、問題の意味をあまりわかっていない生徒もいました。 これまで、その子の状況を見取れていなかったんだなーと感じました。 やっぱり、授業中でもしっかりと立ち止まって互いの理解度を確認することって大切。
もっと、そういう機会を取り入れていきたいと思います。。。 反省!
あと、読み書きに困難のある生徒に対しては、フォニックスと音韻操作のトレーニングが効果があるということを知ったので、その辺も授業と個別指導でやっていきたいなーって考えています。 5月からは復習ということでフォニックスを帯活動として取り入れています。 人数が少ないので、それぞれの課題を見取りやすいのは離島の良いところかも。 フォニックスの指導はALTにリードしてもらって、授業ノートに生徒の様子を書き込んでいます。 彼らの課題がある程度わかってきたら、個別の指導に移りたいと思います。 フォニックスの指導は写真の本を参考にしているので、去年よりもちょっと良い感じになってきました。あとは、音韻操作のトレーニングなんですが、具体的にどんなトレーニングが必要なのか、まだわかっていません。。。 良い参考文献があればいいのですが。。。

書いていて、自分の課題がわかってきました。6月に入りました!!気合いを入れ直してがんばります!!
読み書きに困り感がある生徒の指導が課題。
最近思っているのは、授業のユニバーサルデザイン(UD)の視点をもっと大切にしていくこと、それから個別の支援が必要だろうなーって思っています。
UDは、特別な支援が必要な子に対する手立てが、他の子にも助かる手立てで、みんなが「わかる」とか「できる」っていう授業をめざそうって考え方です。(俺の理解ではw) 3つの視点を大切にしていたと思います。
①視角化:映像、写真、絵、実物教材とか、実際に演じてみるとか。けっこう人間って視覚的な情報に頼ってる部分大きいみたいなので、しっかりと見て、確認できることって大切みたい。
②焦点化:「1時間、1目標」みたいな感じで、1時間になんでも詰め込みすぎないで、シンプルにすることがわかりやすさにつながるみたいな。
③共有化:子ども達が理解したことを(ペアとかで)共有することで、みんな一緒に進んでいくってこと。プラス、互いの意見を交換しながら学び合うってことだったと思う。
今は、前よりもこれらの視点を意識して授業計画しているつもりです。
①視角化
英語の授業では特に視覚教材って大切。 題材に興味を持ってもらったり、意味を類推させるために必要になります。
前からパワポを使っていたんだけど、できるだけシンプルに!っていうのを意識していました。 やっぱり、忙しいとパワポのアニメーションにこだわるのはできないし、それだったら、シンプルに写真を並べるだけでも生徒の興味・関心を高めたり、理解を深められるようなClassroom Englishのスキルを上げた方が良いなーって思ってました。
でも、最近は、もっとわかりやすさを追求しよう!ってことで、けっこうアニメーションにこだわったり、見やすさを意識した色を使ったり、注目しやすいように色を変えるとか工夫しています。 今思っているのは、パワポのスキルをアップさせて授業準備の効率的にできるようにしようってことです。 あと、1回苦労して作ると、あとは同じアニメーションの設定で、コピペするだけでいいので、だいぶ授業準備の時間は短縮されました。 パワポのスキルがあがると、あんな活動もいいなーとかいろいろアイディアがでてきます。 今年はこだわってやっていきたいなーって思っています。
あとは、パワポだけでなく、関連する映像とかをもっともっと使えたらいいなー。生徒の興味を引きつけるだけじゃなくて、題材をもっと「自分事」として捉えられるようにできたらいいなー。今は、まだまだ教科書をどうわかりやすか教えるかってところの方に意識が向いていて、教科書を超えて、子ども達と学ぶってところをやりたいなー。でも、まだちょっと時間がかかりそう。。。
②焦点化
学生のころから、「めあて」とか「目標」を示すのがあんまり好きじゃないタイプでした。「英語を勉強!勉強!勉強!みたいにしたくない。楽しみながら自然と身につけてほしい!」みたいな考えがあったのでw
今も最初から目標を提示すると「マジックの種明かし」をしているような感じで、個人的にしっくりこないので、できるだけ導入を終えて興味・
関心が高まったときに提示したいなーと思っています。 だけど、そうしていたら、目標を提示するのを忘れたりもするし、復習に予想以上に時間がかかってしまったときに、授業の終わり20分前で目標の提示とかあるんだけど。。。 どうしたらいいんですかね。。。
とりあえず、特別支援教育の視点から目標を提示することは大切みたいです。勉強のできる「勘のいい子」は目標の提示なしでも、自然と「こんなことを勉強するんだー」っていうのがわかるみたいですが、特別な支援の必要な子やスローラーナー(Slow Leaner)には、方向性がわからないままさまよっているような感じだそうです。だから、できるだけ授業の早い段階で目標を提示したいのですが。。。 この辺はまだまだ工夫が必要です。
③共有化
なんか、書いていて気づいたけど、授業中にこの視点をあまり意識してこなかったなーと。 最近、3年生の授業でT / F Questionsをやったとに、答えの理由をペアで確認してもらいました。 そしたら、問題の意味をあまりわかっていない生徒もいました。 これまで、その子の状況を見取れていなかったんだなーと感じました。 やっぱり、授業中でもしっかりと立ち止まって互いの理解度を確認することって大切。
もっと、そういう機会を取り入れていきたいと思います。。。 反省!
あと、読み書きに困難のある生徒に対しては、フォニックスと音韻操作のトレーニングが効果があるということを知ったので、その辺も授業と個別指導でやっていきたいなーって考えています。 5月からは復習ということでフォニックスを帯活動として取り入れています。 人数が少ないので、それぞれの課題を見取りやすいのは離島の良いところかも。 フォニックスの指導はALTにリードしてもらって、授業ノートに生徒の様子を書き込んでいます。 彼らの課題がある程度わかってきたら、個別の指導に移りたいと思います。 フォニックスの指導は写真の本を参考にしているので、去年よりもちょっと良い感じになってきました。あとは、音韻操作のトレーニングなんですが、具体的にどんなトレーニングが必要なのか、まだわかっていません。。。 良い参考文献があればいいのですが。。。

書いていて、自分の課題がわかってきました。6月に入りました!!気合いを入れ直してがんばります!!
2017年05月08日
GWが終わった! 「べしゃりマスター」
GWが終わりました。 子どもが産まれて初めてのGW。去年までは自分の好きなことばっかしてたんだけど、今年はずっと子どもと一緒に過ごしました。子どもが産まれると生活が変わりますね。産まれて1ヵ月ということで、実家に子どもを連れて行ったり、両親にうちに来てもらって飯を食べたり、幸せなひとときでした。
子育てって大変ですね。寝ているときや落ち着いているときは、天使のようにかわいい!いろんな表情するから見ていて飽きない。
でも、ギャン泣きしたら大慌て!笑 あれっミルクあげたばっかりじゃん? オムツも変えたよー?? なんで-?ってときがつらい。
そんなときに頼りになるのが妻です。いつもありがとう。 いいお父さんになれるように頑張ります!!
今日は、去年から力を入れているスピーキングの帯活動「べしゃりマスター」について少し書きます。
去年、英語教育の達人セミナー(達セミ)に参加して教えていただいた活動です。あ、べしゃりマスターというのは勝手につけました。笑
べしゃりマスターは毎週トピックを決めて(週に多いときで4コマ)、そのトピックについて話す活動です。
まずは、教師とALTのSmall Talkで生徒とインタラクションをしながら、モデルを示して、ペア活動に入ります。
ペアを変えながら、話すので1日に2人くらいと話すことになるんですが、うちの学校は少人数のクラスなので、3日目になるとほとんどの相手の内容をわかっているということも。。。苦笑
それでも、みんな意欲的に取り組んでくれています!!
相手の話している内容を参考に、少しずつ内容を深めたり、表現の幅を広げていけるのがポイント!!
なんですが、内容を理解することと質問を考えることが優先されていて、「あー、こんなふうに言えば良いのかー!」
ってできるのはまだまだ英語が得意な子かなー。
この部分はもう少しじっくり見守りたいと思います。
あと、少人数なので、教師とALTがまわりながらフィードバックできるのもいいところ。
机間支援をしていると、「せんせー、〇〇ってなんっていうんですかー」みたいな質問もあります。
生徒が困っているときに介入することもあるんですが、recastよりもnegative feedbackが多いのはい良いのか悪いのかハテナ笑
生徒は直されても、それをマイナスな方向に捉えていないと思っているのですが。。。
去年からべしゃりマスターを継続しているので、けっこう話す力付いている気がしてます。
今年は、さらにいろいろ工夫しているつもりです。
トピックに合わせて文法的なポイントを説明したりやスピーキングのスキルについて指導しています。
この部分に関しては、英語と日本語を交ぜてPPTを使ってやってます。
こんな感じ↓↓↓


PPTでの明示的な説明をいれたことによって、生徒が自分のスピーキングについてモニタリングできるかなーと思っています。
去年から自分の英語スキルをメタなレベルから捉えて、自分で考えて学習が進められることをテーマに指導しているですが、明示的な説明を入れることによって、自分のスピーキング力をメタなレベルから捉えるために役立っているかなーって感じています。
例えば・・・「質問に対して、一文で答えているから話の内容が広がらない、もう一文付け加えてみよう」みたいな。
それから、「話しが詰まった場合には、『What else did you do?(他に何したの?)』等を使って話題を変えてみよう!」とか
授業の終わりにふり返りを書いてもらったら、「今日は1文足すことできた。」みたいなふり返りを書いてくれる子もいるので、スピーキングのスキルとか文法に関する明示的な説明って役立っている気がしています。
2年生は1回目は45秒、2回目は1分間。3年生は2回とも1分間会話を続けることを目標にしています。
達セミの先生方から教えてもらった方法ですが、「分からない単語は日本語で言ってもOK!」
生徒には「出川イングリッシュ」でも全然OK!って行っています。
なので、わからないことは日本語で行ったり、単語だけを並べて伝えている生徒もいます。
特に2年生では質問を英語で正しい文法で言うのはまだまだ難しいので、単語の語尾をあげて言うことで質問しています。
「What shopping?」みたいな! 「What did you buy?」がまだ言えていないのです。。。
こんな感じで生徒の中間言語(inter-language/learner language)を認めるって大切かなと思います。達セミの先生方から学べて本当に良かった!あと、出川インギリッシュの影響は大きい! 生徒も「これでいいんだ!」って思えて、楽しみながらやってます。

あと、2日目か3日目には話した内容を書いてみるという活動をやっています。

生徒は5分間で自分が話したことや相手からされた質問を書いていきます。

ポイントはまたまたですが、中間言語(inter-language)を認めるということです。授業ではワークシートの上の方に、話したことを書いていきますが、わからない単語はだいだいのスペルでもいい。もしくは、カタカナや日本語でも言いことにしてます。
だけど、家庭学習では分からない単語を調べて、練習して、できるだけ正確に英文にしていみることを求めています。
そのためにワークシートの中段には意味調べのスペース用意していて、その下には自分で直した英文を書いてもらっています。
提出した英文はALTがチェックしてくれます。うちの学校はALTが毎日いる!恵まれた環境!
2年生は文法的なミスを直してあげるのですが、3年生は赤ペンでチェックして自分たちで何が違うのかを考えてもらっています。
意欲のある生徒は再提出をしてくれます。うれしい-!! ホントはここまでみんなに求めた方がいいんだろうなー。
あと、最近になってですが、書いてくれた作文の内容についての質問をALTに書いてもらっています。そうすることによって、もっと内容を深めたり、関連する内容に広げたりできるかなーと思ってやってます。まだまだ成果はでていませんが。。。
スピーキングの帯活動なので、正確性よりも流暢性を目的にして、間違いを恐れずにとにかく継続することを大切にしています。
あ、書いていて気づいたのですが、明示的な説明がスピーキング最中に正確性を意識しすぎることにつながらないかという心配が。。。
そこは注意しつつ、進めていくということ!!!笑
なんか、書いていてどんどんまとまらなくなっているのですが。。。
それでも、やっぱり、ブログに書くっていいですね。自分自身のリフレクションになります。他の活動も書いてみよう。
子育てって大変ですね。寝ているときや落ち着いているときは、天使のようにかわいい!いろんな表情するから見ていて飽きない。
でも、ギャン泣きしたら大慌て!笑 あれっミルクあげたばっかりじゃん? オムツも変えたよー?? なんで-?ってときがつらい。
そんなときに頼りになるのが妻です。いつもありがとう。 いいお父さんになれるように頑張ります!!
今日は、去年から力を入れているスピーキングの帯活動「べしゃりマスター」について少し書きます。
去年、英語教育の達人セミナー(達セミ)に参加して教えていただいた活動です。あ、べしゃりマスターというのは勝手につけました。笑
べしゃりマスターは毎週トピックを決めて(週に多いときで4コマ)、そのトピックについて話す活動です。
まずは、教師とALTのSmall Talkで生徒とインタラクションをしながら、モデルを示して、ペア活動に入ります。
ペアを変えながら、話すので1日に2人くらいと話すことになるんですが、うちの学校は少人数のクラスなので、3日目になるとほとんどの相手の内容をわかっているということも。。。苦笑
それでも、みんな意欲的に取り組んでくれています!!
相手の話している内容を参考に、少しずつ内容を深めたり、表現の幅を広げていけるのがポイント!!
なんですが、内容を理解することと質問を考えることが優先されていて、「あー、こんなふうに言えば良いのかー!」
ってできるのはまだまだ英語が得意な子かなー。
この部分はもう少しじっくり見守りたいと思います。
あと、少人数なので、教師とALTがまわりながらフィードバックできるのもいいところ。
机間支援をしていると、「せんせー、〇〇ってなんっていうんですかー」みたいな質問もあります。
生徒が困っているときに介入することもあるんですが、recastよりもnegative feedbackが多いのはい良いのか悪いのかハテナ笑
生徒は直されても、それをマイナスな方向に捉えていないと思っているのですが。。。
去年からべしゃりマスターを継続しているので、けっこう話す力付いている気がしてます。
今年は、さらにいろいろ工夫しているつもりです。
トピックに合わせて文法的なポイントを説明したりやスピーキングのスキルについて指導しています。
この部分に関しては、英語と日本語を交ぜてPPTを使ってやってます。
こんな感じ↓↓↓


PPTでの明示的な説明をいれたことによって、生徒が自分のスピーキングについてモニタリングできるかなーと思っています。
去年から自分の英語スキルをメタなレベルから捉えて、自分で考えて学習が進められることをテーマに指導しているですが、明示的な説明を入れることによって、自分のスピーキング力をメタなレベルから捉えるために役立っているかなーって感じています。
例えば・・・「質問に対して、一文で答えているから話の内容が広がらない、もう一文付け加えてみよう」みたいな。
それから、「話しが詰まった場合には、『What else did you do?(他に何したの?)』等を使って話題を変えてみよう!」とか
授業の終わりにふり返りを書いてもらったら、「今日は1文足すことできた。」みたいなふり返りを書いてくれる子もいるので、スピーキングのスキルとか文法に関する明示的な説明って役立っている気がしています。
2年生は1回目は45秒、2回目は1分間。3年生は2回とも1分間会話を続けることを目標にしています。
達セミの先生方から教えてもらった方法ですが、「分からない単語は日本語で言ってもOK!」
生徒には「出川イングリッシュ」でも全然OK!って行っています。
なので、わからないことは日本語で行ったり、単語だけを並べて伝えている生徒もいます。
特に2年生では質問を英語で正しい文法で言うのはまだまだ難しいので、単語の語尾をあげて言うことで質問しています。
「What shopping?」みたいな! 「What did you buy?」がまだ言えていないのです。。。
こんな感じで生徒の中間言語(inter-language/learner language)を認めるって大切かなと思います。達セミの先生方から学べて本当に良かった!あと、出川インギリッシュの影響は大きい! 生徒も「これでいいんだ!」って思えて、楽しみながらやってます。

あと、2日目か3日目には話した内容を書いてみるという活動をやっています。

生徒は5分間で自分が話したことや相手からされた質問を書いていきます。

ポイントはまたまたですが、中間言語(inter-language)を認めるということです。授業ではワークシートの上の方に、話したことを書いていきますが、わからない単語はだいだいのスペルでもいい。もしくは、カタカナや日本語でも言いことにしてます。
だけど、家庭学習では分からない単語を調べて、練習して、できるだけ正確に英文にしていみることを求めています。
そのためにワークシートの中段には意味調べのスペース用意していて、その下には自分で直した英文を書いてもらっています。
提出した英文はALTがチェックしてくれます。うちの学校はALTが毎日いる!恵まれた環境!
2年生は文法的なミスを直してあげるのですが、3年生は赤ペンでチェックして自分たちで何が違うのかを考えてもらっています。
意欲のある生徒は再提出をしてくれます。うれしい-!! ホントはここまでみんなに求めた方がいいんだろうなー。
あと、最近になってですが、書いてくれた作文の内容についての質問をALTに書いてもらっています。そうすることによって、もっと内容を深めたり、関連する内容に広げたりできるかなーと思ってやってます。まだまだ成果はでていませんが。。。
スピーキングの帯活動なので、正確性よりも流暢性を目的にして、間違いを恐れずにとにかく継続することを大切にしています。
あ、書いていて気づいたのですが、明示的な説明がスピーキング最中に正確性を意識しすぎることにつながらないかという心配が。。。
そこは注意しつつ、進めていくということ!!!笑
なんか、書いていてどんどんまとまらなくなっているのですが。。。
それでも、やっぱり、ブログに書くっていいですね。自分自身のリフレクションになります。他の活動も書いてみよう。
2017年04月20日
久しぶりの投稿
定期的に書こうと思いながら、1年以上が経過・・・w
今年は去年よりも余裕があるので、自分のリフレクションのために書いていこうと思います。
昨年度は、教務主任と言うことで、今考えるとけっこう空き時間は学校のことを考えていたように思います。
去年も授業準備に手を抜いていたつもりはないんだけれど、今年は断然、余裕があって、授業のことにもっともっと時間を割くことができています。
楽しい!
これまでの2年間で全学年を担当していたので、1年間の見通しも持てるし、これまでの教材をもとに、アレンジしながら教材研究ができます。
去年も授業ノートを作っていたんだけど、だんだん活用しなくなっていたのですが、今年は毎時間のリフレクションを書き込むことができています。
今のところ欠かさず!
やはり、リフレクションって大切。 自分自身と生徒の課題を見つめ直して、課題を乗り越えるための手立てを考えていく。
授業改善ってそれの繰り返しなのかなーって思います。 今年は、この島ラストの年。
がっつり教材研究して力をつけたい!!
今年は、スピーキングの帯活動に力を入れたいと思っています。教科書の2・3単元ごとにプロジェクトが設定されているんだけど、そのプロジェクトにつなげられるように、日々の授業からスピーキングとかスピーキングからのライティングとかを取り組んでいきたいと思っています。
次の投稿ではスピーキングの帯活動「べしゃりマスター」について書きたいと思います。
今年は去年よりも余裕があるので、自分のリフレクションのために書いていこうと思います。
昨年度は、教務主任と言うことで、今考えるとけっこう空き時間は学校のことを考えていたように思います。
去年も授業準備に手を抜いていたつもりはないんだけれど、今年は断然、余裕があって、授業のことにもっともっと時間を割くことができています。
楽しい!
これまでの2年間で全学年を担当していたので、1年間の見通しも持てるし、これまでの教材をもとに、アレンジしながら教材研究ができます。
去年も授業ノートを作っていたんだけど、だんだん活用しなくなっていたのですが、今年は毎時間のリフレクションを書き込むことができています。
今のところ欠かさず!
やはり、リフレクションって大切。 自分自身と生徒の課題を見つめ直して、課題を乗り越えるための手立てを考えていく。
授業改善ってそれの繰り返しなのかなーって思います。 今年は、この島ラストの年。
がっつり教材研究して力をつけたい!!
今年は、スピーキングの帯活動に力を入れたいと思っています。教科書の2・3単元ごとにプロジェクトが設定されているんだけど、そのプロジェクトにつなげられるように、日々の授業からスピーキングとかスピーキングからのライティングとかを取り組んでいきたいと思っています。
次の投稿ではスピーキングの帯活動「べしゃりマスター」について書きたいと思います。
2016年01月28日
パフォーマンス・テストに基づいた年間計画??
定期的に書こうと思いながら、全然書いていませんでいた。
12月に教科書内容の授業に関して書いていたのですが、がっつり書こうとしすぎて、書けませんでした。
これからは気楽に書いていきたいと思います。
もう1月も最後の週になりました。来週からは2月。あっという間に、今年度も終わるんでしょうね。
今年は赴任してから、新しい環境や新しい教科書に慣れていなかったため、授業でも見通しを持つことがあまりできていませんでした。
単元ごとには計画を立てていたのですが、年間を見通した計画は立てられていませんでした。
それでも、自分なりの手応えは感じつつ(まだまだ課題だらけですけど)、次年度につながるような指導はしてきたつもりです。
先日、教育事務所からのアンケートで、パフォーマンステストについての調査がありました。自分ではこれまでに比べてパフォーマンステストを実施していたつもりですが、足りない部分があることに気づきました。
○英作文が中心になっていること。
○作文をしてからのプレゼンテーションによるスピーキングテストに偏っていること。
インタビューテストや即興でコミュニケーションを一定の時間続けるテストなどが必要かなと思います。
もっと、いろいろなパフォーマンステストを実施しないと、指導も偏ってしまうし、生徒のコミュニケーション能力も偏ってしまいます。
次年度はその辺をしっかり考えて、年間計画を立てたいと思っています。あ、立てているところです。
今、参考にしている文献は、



と言う本です。来年度はめっちゃお世話になりそうです。
まだ、すべてを熟読できていませんが、今のところの感想として。
①パフォーマンステストを含んだ授業実践のアクションリサーチが載っているのが参考になる。
②指導の流れとテストの実施方法、ルーブリック(採点基準)が載っている。
③各学年で学習する文法事項と合っている。内容も教科書と合わせやすい。そのまま実施できるものが多い。
という感じです。
今は、教科書会社が作成してくれている年間指導計画と教科書と前述の本を見ながら、どのようなパフォーマンステストをしようか検討しているところです。
パフォーマンステストが単元の目標となって、それに向かって指導をプランできるといいなーって思っています。特に、今年度は帯活動が行き当たりばったりな部分があったので、パフォーマンステストに向けて計画的に入れいきたいです。
計画していてワクワクするし、次年度が楽しみになってきました。
(その前に今年度の授業をしっかりしないといけないけど!)
本当は、3年生からバックウォード(Backward)に計画を立てる方がいいんだろうけど、自分が担任している2年生からやってしまっている。笑 たぶん、大丈夫でしょう。
パフォーマンス・テストの年間計画表を作れたらいいなーと思っています。 よし、少しがんばろう。
12月に教科書内容の授業に関して書いていたのですが、がっつり書こうとしすぎて、書けませんでした。
これからは気楽に書いていきたいと思います。
もう1月も最後の週になりました。来週からは2月。あっという間に、今年度も終わるんでしょうね。
今年は赴任してから、新しい環境や新しい教科書に慣れていなかったため、授業でも見通しを持つことがあまりできていませんでした。
単元ごとには計画を立てていたのですが、年間を見通した計画は立てられていませんでした。
それでも、自分なりの手応えは感じつつ(まだまだ課題だらけですけど)、次年度につながるような指導はしてきたつもりです。
先日、教育事務所からのアンケートで、パフォーマンステストについての調査がありました。自分ではこれまでに比べてパフォーマンステストを実施していたつもりですが、足りない部分があることに気づきました。
○英作文が中心になっていること。
○作文をしてからのプレゼンテーションによるスピーキングテストに偏っていること。
インタビューテストや即興でコミュニケーションを一定の時間続けるテストなどが必要かなと思います。
もっと、いろいろなパフォーマンステストを実施しないと、指導も偏ってしまうし、生徒のコミュニケーション能力も偏ってしまいます。
次年度はその辺をしっかり考えて、年間計画を立てたいと思っています。あ、立てているところです。
今、参考にしている文献は、



と言う本です。来年度はめっちゃお世話になりそうです。
まだ、すべてを熟読できていませんが、今のところの感想として。
①パフォーマンステストを含んだ授業実践のアクションリサーチが載っているのが参考になる。
②指導の流れとテストの実施方法、ルーブリック(採点基準)が載っている。
③各学年で学習する文法事項と合っている。内容も教科書と合わせやすい。そのまま実施できるものが多い。
という感じです。
今は、教科書会社が作成してくれている年間指導計画と教科書と前述の本を見ながら、どのようなパフォーマンステストをしようか検討しているところです。
パフォーマンステストが単元の目標となって、それに向かって指導をプランできるといいなーって思っています。特に、今年度は帯活動が行き当たりばったりな部分があったので、パフォーマンステストに向けて計画的に入れいきたいです。
計画していてワクワクするし、次年度が楽しみになってきました。
(その前に今年度の授業をしっかりしないといけないけど!)
本当は、3年生からバックウォード(Backward)に計画を立てる方がいいんだろうけど、自分が担任している2年生からやってしまっている。笑 たぶん、大丈夫でしょう。
パフォーマンス・テストの年間計画表を作れたらいいなーと思っています。 よし、少しがんばろう。
2015年12月04日
Face Tiimeを使っての交流学習①
今日は、県内の離島との交流学習。 Face TimeというiPadのアプリを使って、インターネットを通しての交流でした。
前回は、1年生に自己紹介をテーマにShow & Tellをしてもらいました。今回は、1年生の身近な人の紹介。
1年生は三単現の「s」を学習したので、自分の家族や好きな有名人について紹介するというタスク。
発表も、それまでの取組もみんな一生懸命がんばってくれました!! 期待以上の内容を考えてくれました。
交流学習までに3時間をかけて準備をしたので、ふり返ってみたいと思います。たぶん、本来なら2時間程度で準備をしないといけないんだけど、オーバーしてしまいました。
1時間目:英作文
①ノートにブレインストーミング
自分が好きな有名人について知っていることをウェビングしていく。何を書くかアイディアを出していく活動。プレ・ライティング活動かな。
まず、有名人を誰にするかでけっこう迷っていました。スポーツ選手や俳優、芸人を紹介することになりました。
②ワークシートに紹介したいことを書いていく。ステップ1

この部分をもっと手立てを考えないといけないなー。教師が英語に直す手助けをしすぎたり、ともすると簡単に答えを教えすぎているんじゃないかなーって感じています。
また、生徒も意欲的なので自分で辞書を調べたり、友だちと教えあったりするんですが、英語の語順にできなかったりします。
やっぱり、「意味順ノート」のような英語の語順を意識させるような英作文のトレーニングを日頃から取り組んでいかないといけないと感じています。
「誰が」 「する・である」 「だれ・なに」 「どこ」 「いつ」
みたいなのを教室掲示したり、プリントで配布して、困ったときには戻れるようにしたいなーって思っています。
③ワークシートに紹介したいことを伝える順番を考えていく。ステップ2
まとまりのある文章を書くことを目指しているので、順番を意識させたり、内容を深める文を付け加えるように指導しています。

He is a professional baseball player.
He is my favorite baseball player.
と書いているのを・・・
He is my favorite professional player.
と言うふうに直していきます。
あと、生徒は思いついた順番に文を書いてしまうので、「この文とこの文は関連してる?」、「どっちの文から話した方が良いのー?」みたいな、気づかせるというよりも、けっこう直接的にフィードバックを与えています。いいのか、悪いのか。
今は、まだ教師がフィードバックを与えて、「直させている」状態。お互いに読み合って、peer feedbackができるように育てていきたいなー。自律した学習者(autonomous leaner)を育てていきたい。 そこまで行くのにはどうすればいいのかまだまだわからないけれど。。。
2時間目
①英作文のつづき
前時の続きをそれぞれのペースで。教師とALTは机間巡視をしながら、添削。生徒6名に対して、指導者2名w すばらしい環境!!
②読む練習 暗記を目標に
この時に、前回のShow & Tellのふり返りシートを再度読ませて、どのようにShow & Tellをしたいか。自分の課題は何か。というのを意識させるべきだった!!ミスった!!せっかく前回の交流学習後に、ふり返りに1時間をかけて、それから音読テスト方法と評価規準も変えて取り組んだのに。。。

みんなよくふり返っているし、次の課題も明確に持っているのに。。。もったいないことをした。次の時間は今回の交流学習のふり返りをするので、その時に比較しながら次の課題を見つけていきたいと思います。
③みんなで発表
席を合わせてみんなの顔が見える状態で、すわったまま発表。まだまだ暗記はできていないので、原稿を見ながらRead and Look-upのように発表してもらいました。
その中で、それぞれの良いところを話し合いました。
ある生徒の発表で
Hello, everyone. Look at this picture.
から始まっていたのをみんながいいところとして認めたので、クラスみんなその始まりにするようにしました。
(おそらくこの子は教科書のプロジェクトの部分を参考にしていると思います。)
もしかすると、はじめから教師が設定しそうなところですが、生徒から出て来て、それをみんなが学んだっていうのはいいかなーって思います。
3時間目
①有名人の写真の選択。カード作り。
教師のパソコンで有名人の写真を選んでもらって、それをすぐに職員室でプリントアウト。画用紙に貼ってもらいました。
②カードをもっての練習。
2つのグループに分かれて、iPadを使って練習。 前回、声が小さいという課題があったので、少し離れたところから動画を撮って、その後はグループでリフレクション。iPadの映像をみながら、下のワークシートに良かったところと良くしたいところを書いてもらいました。

プランでは、質問を考える時間を取るつもりだったんですが、残念ながらタイムオーバー。。。前回も質問タイムが課題だったので、これから改善していきたいと思います。
やっぱり、「相手のプレゼンを聞いて自分で質問を考える力」と「質問に即座に答える力」っていうのをつけていきたいなー。
そんな指導はまだまだできていないなー。
また、子どもたちとのふり返りが終わったら、交流学習当日のふり返りをつぶやいていきたいと思います。
ふー、今日は気合いを入れて書いたから、なんだか疲れたな。。。笑
前回は、1年生に自己紹介をテーマにShow & Tellをしてもらいました。今回は、1年生の身近な人の紹介。
1年生は三単現の「s」を学習したので、自分の家族や好きな有名人について紹介するというタスク。
発表も、それまでの取組もみんな一生懸命がんばってくれました!! 期待以上の内容を考えてくれました。
交流学習までに3時間をかけて準備をしたので、ふり返ってみたいと思います。たぶん、本来なら2時間程度で準備をしないといけないんだけど、オーバーしてしまいました。
1時間目:英作文
①ノートにブレインストーミング
自分が好きな有名人について知っていることをウェビングしていく。何を書くかアイディアを出していく活動。プレ・ライティング活動かな。
まず、有名人を誰にするかでけっこう迷っていました。スポーツ選手や俳優、芸人を紹介することになりました。
②ワークシートに紹介したいことを書いていく。ステップ1

この部分をもっと手立てを考えないといけないなー。教師が英語に直す手助けをしすぎたり、ともすると簡単に答えを教えすぎているんじゃないかなーって感じています。
また、生徒も意欲的なので自分で辞書を調べたり、友だちと教えあったりするんですが、英語の語順にできなかったりします。
やっぱり、「意味順ノート」のような英語の語順を意識させるような英作文のトレーニングを日頃から取り組んでいかないといけないと感じています。
「誰が」 「する・である」 「だれ・なに」 「どこ」 「いつ」
みたいなのを教室掲示したり、プリントで配布して、困ったときには戻れるようにしたいなーって思っています。
③ワークシートに紹介したいことを伝える順番を考えていく。ステップ2
まとまりのある文章を書くことを目指しているので、順番を意識させたり、内容を深める文を付け加えるように指導しています。

He is a professional baseball player.
He is my favorite baseball player.
と書いているのを・・・
He is my favorite professional player.
と言うふうに直していきます。
あと、生徒は思いついた順番に文を書いてしまうので、「この文とこの文は関連してる?」、「どっちの文から話した方が良いのー?」みたいな、気づかせるというよりも、けっこう直接的にフィードバックを与えています。いいのか、悪いのか。
今は、まだ教師がフィードバックを与えて、「直させている」状態。お互いに読み合って、peer feedbackができるように育てていきたいなー。自律した学習者(autonomous leaner)を育てていきたい。 そこまで行くのにはどうすればいいのかまだまだわからないけれど。。。
2時間目
①英作文のつづき
前時の続きをそれぞれのペースで。教師とALTは机間巡視をしながら、添削。生徒6名に対して、指導者2名w すばらしい環境!!
②読む練習 暗記を目標に
この時に、前回のShow & Tellのふり返りシートを再度読ませて、どのようにShow & Tellをしたいか。自分の課題は何か。というのを意識させるべきだった!!ミスった!!せっかく前回の交流学習後に、ふり返りに1時間をかけて、それから音読テスト方法と評価規準も変えて取り組んだのに。。。

みんなよくふり返っているし、次の課題も明確に持っているのに。。。もったいないことをした。次の時間は今回の交流学習のふり返りをするので、その時に比較しながら次の課題を見つけていきたいと思います。
③みんなで発表
席を合わせてみんなの顔が見える状態で、すわったまま発表。まだまだ暗記はできていないので、原稿を見ながらRead and Look-upのように発表してもらいました。
その中で、それぞれの良いところを話し合いました。
ある生徒の発表で
Hello, everyone. Look at this picture.
から始まっていたのをみんながいいところとして認めたので、クラスみんなその始まりにするようにしました。
(おそらくこの子は教科書のプロジェクトの部分を参考にしていると思います。)
もしかすると、はじめから教師が設定しそうなところですが、生徒から出て来て、それをみんなが学んだっていうのはいいかなーって思います。
3時間目
①有名人の写真の選択。カード作り。
教師のパソコンで有名人の写真を選んでもらって、それをすぐに職員室でプリントアウト。画用紙に貼ってもらいました。
②カードをもっての練習。
2つのグループに分かれて、iPadを使って練習。 前回、声が小さいという課題があったので、少し離れたところから動画を撮って、その後はグループでリフレクション。iPadの映像をみながら、下のワークシートに良かったところと良くしたいところを書いてもらいました。

プランでは、質問を考える時間を取るつもりだったんですが、残念ながらタイムオーバー。。。前回も質問タイムが課題だったので、これから改善していきたいと思います。
やっぱり、「相手のプレゼンを聞いて自分で質問を考える力」と「質問に即座に答える力」っていうのをつけていきたいなー。
そんな指導はまだまだできていないなー。
また、子どもたちとのふり返りが終わったら、交流学習当日のふり返りをつぶやいていきたいと思います。
ふー、今日は気合いを入れて書いたから、なんだか疲れたな。。。笑
2015年12月03日
「書くこと」の指導
最近、興味ある分野はライティング指導と効果的なフィードバック。
どうやって指導と評価をつないでいくか。 表現の技能、「書くこと」、「話すこと」の指導と評価って難しい。もっともっと勉強しなければ。。。
毎月、(一応)購読している『英語教育』という雑誌でライティングに関する特集が組まれていました。

いつもは、届いてもなかなか読まずに、積読になっているのだけど、ちょうど「書くこと」の指導をもっと充実させたいので、手に取ってみました。
その中でも安部肇子先生の実践がおもしろい!と思ったので、実際にやってみたいと思っています。
帯活動で「1日1文」を積み重ねるという内容で、多くの先生が取り組んでいるような実践かなと思ったのですが、随所に工夫が見られていて、とても参考になりました。
簡単に方法を書きたいと思います。
①質問シート
・目標の文法項目を引き出すような質問が書かれている。
・後でまとまりのある文章が書きやすいように、質問に「流れ」を入れ込んでおく。
今作成中なんですが・・・ 流れを作るのが案外難しい。。。教材研究の面白いところかな。教師の腕の見せどころ?
こんな感じで作っていますが・・・

目標の文法項目を含めるのはいいんだけど、文章の流れを引き出すような質問が難しいです。
もうすこし、「こんな文章を書かせたい」っていう部分が固まったらできるのかも。
まぁ、とりあえず、最初から完璧にはできないので、やってみてまたふり返りたいと思っています。
②作文シート
・質問シートの答えを書くシート。
・縦に2つに分けていて、左側には例文を。右側には生徒が例文を参考に答えを書けるスペース。
・この部分を変えれば、オリジナル文が書けるというところに下線を入れる。

やっぱり、下線部を入れ変えるだけってところが、スローラーナーにもわかりやすいかなーって思います。
やってみて、生徒の感想を聞いてみたいと思います。
この他にも、様々な工夫があって、とても参考になりました。
安部先生が書かれているように、「シンプル」で「手間がかからない」ので誰でも実践できそうです。
詳しくは、以下の文献を参考にしてください。
安部肇子(2015).「『1日1文』帯活動の積み重ねでまとまった文作成につなげる」,『英語教育』 64(10), pp16-17.
久しぶりにAPAのスタイルで参考文献を載せたw 順番がわからなったから、ネットで調べました。当たってるかな?w
どうやって指導と評価をつないでいくか。 表現の技能、「書くこと」、「話すこと」の指導と評価って難しい。もっともっと勉強しなければ。。。
毎月、(一応)購読している『英語教育』という雑誌でライティングに関する特集が組まれていました。

いつもは、届いてもなかなか読まずに、積読になっているのだけど、ちょうど「書くこと」の指導をもっと充実させたいので、手に取ってみました。
その中でも安部肇子先生の実践がおもしろい!と思ったので、実際にやってみたいと思っています。
帯活動で「1日1文」を積み重ねるという内容で、多くの先生が取り組んでいるような実践かなと思ったのですが、随所に工夫が見られていて、とても参考になりました。
簡単に方法を書きたいと思います。
①質問シート
・目標の文法項目を引き出すような質問が書かれている。
・後でまとまりのある文章が書きやすいように、質問に「流れ」を入れ込んでおく。
今作成中なんですが・・・ 流れを作るのが案外難しい。。。教材研究の面白いところかな。教師の腕の見せどころ?
こんな感じで作っていますが・・・

目標の文法項目を含めるのはいいんだけど、文章の流れを引き出すような質問が難しいです。
もうすこし、「こんな文章を書かせたい」っていう部分が固まったらできるのかも。
まぁ、とりあえず、最初から完璧にはできないので、やってみてまたふり返りたいと思っています。
②作文シート
・質問シートの答えを書くシート。
・縦に2つに分けていて、左側には例文を。右側には生徒が例文を参考に答えを書けるスペース。
・この部分を変えれば、オリジナル文が書けるというところに下線を入れる。

やっぱり、下線部を入れ変えるだけってところが、スローラーナーにもわかりやすいかなーって思います。
やってみて、生徒の感想を聞いてみたいと思います。
この他にも、様々な工夫があって、とても参考になりました。
安部先生が書かれているように、「シンプル」で「手間がかからない」ので誰でも実践できそうです。
詳しくは、以下の文献を参考にしてください。
安部肇子(2015).「『1日1文』帯活動の積み重ねでまとまった文作成につなげる」,『英語教育』 64(10), pp16-17.
久しぶりにAPAのスタイルで参考文献を載せたw 順番がわからなったから、ネットで調べました。当たってるかな?w
2015年11月27日
期末テストをふり返る
今週は、うちの学校は期末テスト。3日間なので、子どもたちも大変だと思います。
うちの学校は学校行事だけでなく、村の行事にも中学生が大きく関わります。なので、2学期は本当に大忙し。
それでも、どの行事にも一生懸命取り組む子どもたちの姿には感動させられます。
中間テストが終わったと思ったら、学習発表会への取組が始まり、その間に小中合同のハロウィン・パーティがあったり、
校区内の小学校の運動会に役員として参加したり、漢検を挟んでからの学習発表会。
その後、村の運動会の役員をして、中文祭ではシュガーホールまで行って太鼓の演舞を披露して、次の日はまた奥武山で離島フェアー。
からの-、期末テスト
改めて行事の多さに驚かされます。。。
子どもたちが一生懸命な姿を見ていると、本当に涙が出るくらい心が揺さぶられます。
一方で、彼らがゆっくり休んだり、落ち着いて勉強する時間は確保できていないように思えます。。。
このような環境なので、テストに向けて、授業の中で復習するような工夫を自分なりにしてみました。
うちの中学校の生徒はリスニングが強くて、文法や書くことに課題があるという傾向なので、前回の中間テストから文法問題を授業の中で総復習する時間を取ったり、課題プリントを出して、文法の定着とテストに慣れるトレーニングをしました。(これまでは、英作文の復習を中心にしていたのですが、文法もケアしてあげないといけないなーと思うようになったので。)
中間テストが終わって生徒から感想を聞くと・・・
◎文法プリントをやったからテストが解きやすかった。
●単元ごとに文法プリントで復習をしたい。
ということがわかりました。
この子たちは自分の意思や思いを伝えるのが上手なので、彼らの考えを聞きながらできるのは私にとってうれしいことです。
今回は期末テストに向けて・・・
・単元ごとに文法総復習の時間を確保。
テスト前に一気に復習するのではなく、もう少し短いスパンで復習するようにしました。
・テスト前には、課題プリントを配布。
ここまでやるべきなのかなーと思いながら。。。 島を出たら、彼らは自分たちの力で学習しないといけないんだけど。。。 自分に合った学習教材を選んだり、どのような学習方法が自分に合っているか考えさせる機会を奪っていないか。。。
・普段の授業では、各パートで文法問題を解いた後に、条件英作文を書く→ノート提出→教師による添削とノート返却→英語通信での生徒の作品の紹介。という感じにしてみました。他県の先生のブログを読んでいるとけっこう生徒たちの作品を通信にして出しているようです。


↑↑↑ こんな感じで配布しました。
生徒が友だちの英文を読む良い機会になったと思います。実際、友だちの書いたことだから、けっこう集中して読んでいて、「誰がこれ書いたバー!?」、「あいつは○○なの~?」というふうなつぶやきや突っ込みが聞こえました。 読む活動としてもいいし、友だちよりももっとおもしろい文を書こう!っていうモチベーションになってくれたらなーって思っています。
今書いていて、1年生はやっていないんだな。これからは1年生にももっと書くことに取り組んでもらわないと。。。
足りていないなー。その割にはけっこうテストに出しているなー。反省。。。
・英語通信で紹介した生徒の英文を教師が日本語訳して、英作文の対策プリントして配布。
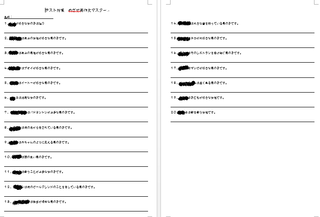
テストでは条件英作文や和文英作文を出題するので、そのトレーニングとして和文英訳にチャレンジしてもらいました。
英語通信に答えが載っているので、わからなかったらチラ見していいよ。ということで、やってもらいました。
テストにもいつくか出題するよーといいながら。子どもたちは頑張ってくれたと思います。
さてさて、今日で全部のテストが終わったので、答案を見ながら、またふり返りたいと思います。
うちの学校は学校行事だけでなく、村の行事にも中学生が大きく関わります。なので、2学期は本当に大忙し。
それでも、どの行事にも一生懸命取り組む子どもたちの姿には感動させられます。
中間テストが終わったと思ったら、学習発表会への取組が始まり、その間に小中合同のハロウィン・パーティがあったり、
校区内の小学校の運動会に役員として参加したり、漢検を挟んでからの学習発表会。
その後、村の運動会の役員をして、中文祭ではシュガーホールまで行って太鼓の演舞を披露して、次の日はまた奥武山で離島フェアー。
からの-、期末テスト
改めて行事の多さに驚かされます。。。
子どもたちが一生懸命な姿を見ていると、本当に涙が出るくらい心が揺さぶられます。
一方で、彼らがゆっくり休んだり、落ち着いて勉強する時間は確保できていないように思えます。。。
このような環境なので、テストに向けて、授業の中で復習するような工夫を自分なりにしてみました。
うちの中学校の生徒はリスニングが強くて、文法や書くことに課題があるという傾向なので、前回の中間テストから文法問題を授業の中で総復習する時間を取ったり、課題プリントを出して、文法の定着とテストに慣れるトレーニングをしました。(これまでは、英作文の復習を中心にしていたのですが、文法もケアしてあげないといけないなーと思うようになったので。)
中間テストが終わって生徒から感想を聞くと・・・
◎文法プリントをやったからテストが解きやすかった。
●単元ごとに文法プリントで復習をしたい。
ということがわかりました。
この子たちは自分の意思や思いを伝えるのが上手なので、彼らの考えを聞きながらできるのは私にとってうれしいことです。
今回は期末テストに向けて・・・
・単元ごとに文法総復習の時間を確保。
テスト前に一気に復習するのではなく、もう少し短いスパンで復習するようにしました。
・テスト前には、課題プリントを配布。
ここまでやるべきなのかなーと思いながら。。。 島を出たら、彼らは自分たちの力で学習しないといけないんだけど。。。 自分に合った学習教材を選んだり、どのような学習方法が自分に合っているか考えさせる機会を奪っていないか。。。
・普段の授業では、各パートで文法問題を解いた後に、条件英作文を書く→ノート提出→教師による添削とノート返却→英語通信での生徒の作品の紹介。という感じにしてみました。他県の先生のブログを読んでいるとけっこう生徒たちの作品を通信にして出しているようです。


↑↑↑ こんな感じで配布しました。
生徒が友だちの英文を読む良い機会になったと思います。実際、友だちの書いたことだから、けっこう集中して読んでいて、「誰がこれ書いたバー!?」、「あいつは○○なの~?」というふうなつぶやきや突っ込みが聞こえました。 読む活動としてもいいし、友だちよりももっとおもしろい文を書こう!っていうモチベーションになってくれたらなーって思っています。
今書いていて、1年生はやっていないんだな。これからは1年生にももっと書くことに取り組んでもらわないと。。。
足りていないなー。その割にはけっこうテストに出しているなー。反省。。。
・英語通信で紹介した生徒の英文を教師が日本語訳して、英作文の対策プリントして配布。
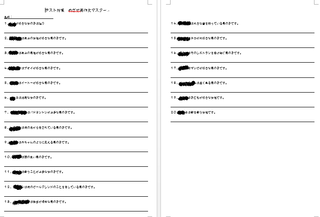
テストでは条件英作文や和文英作文を出題するので、そのトレーニングとして和文英訳にチャレンジしてもらいました。
英語通信に答えが載っているので、わからなかったらチラ見していいよ。ということで、やってもらいました。
テストにもいつくか出題するよーといいながら。子どもたちは頑張ってくれたと思います。
さてさて、今日で全部のテストが終わったので、答案を見ながら、またふり返りたいと思います。
2015年11月19日
うーん。教材研究不足。。。
3年生 TOTAL ENGLISH
Lesson 5はスティービー・ワンダーに関する内容。
今日は、キング牧師のこととかWe are the worldのこととかをネットでチラチラ調べていました。
教科書の内容で、スティービーがキング牧師の誕生日を国民の休日に定めるように動いたっていうのがあって、キング牧師について調べました。
その中でキング牧師が受けた人種差別とか「モンゴメリー・バス・ボイコット事件」について読んでました。なんだか、この人種差別って沖縄が受けている今の辺野古の移設問題と似ているなーって思ってしまいました。マイノリティーの声が届かないような感じが。
この頃、教科書の中身をもっと深めるような授業がしたい。生徒の心を動かすような内容にしたいって思うようになって、なんかできないかと考えながら悶々としてます。
生徒に自分の考えを押しつけないように、だけど、沖縄の問題についても関心を持ってほしいし、沖縄の問題に触れることが教科書内容を自分事と捉えることにつながるようにしたい。
ちょっとがんばってみよう。 テスト前だけど。。。 一歩前に進みたいなー。
Lesson 5はスティービー・ワンダーに関する内容。
今日は、キング牧師のこととかWe are the worldのこととかをネットでチラチラ調べていました。
教科書の内容で、スティービーがキング牧師の誕生日を国民の休日に定めるように動いたっていうのがあって、キング牧師について調べました。
その中でキング牧師が受けた人種差別とか「モンゴメリー・バス・ボイコット事件」について読んでました。なんだか、この人種差別って沖縄が受けている今の辺野古の移設問題と似ているなーって思ってしまいました。マイノリティーの声が届かないような感じが。
この頃、教科書の中身をもっと深めるような授業がしたい。生徒の心を動かすような内容にしたいって思うようになって、なんかできないかと考えながら悶々としてます。
生徒に自分の考えを押しつけないように、だけど、沖縄の問題についても関心を持ってほしいし、沖縄の問題に触れることが教科書内容を自分事と捉えることにつながるようにしたい。
ちょっとがんばってみよう。 テスト前だけど。。。 一歩前に進みたいなー。